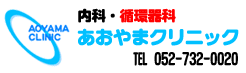
高齢化社会を迎えたわが国では、現在、糖尿病、高脂血症、高血圧症といった、いわゆる生活習慣病が増加し、それに合併する動脈硬化症、 とりわけ冠動脈疾患による死亡が増加傾向を示しています。 高血圧や高コレステロールの人に冠動脈疾患の頻度が高い事は以前より知られていましたが、 1989年Kaplanは、単独でも動脈硬化の危険因子となり得る上半身肥満、耐糖能異常(糖尿病やその前段階である境界型)、高トリクリセリド血症(中性脂肪)、高血圧が同じ人に合併して起こり、そのような人では冠動脈疾患が多発しやすいことを明らかにしました。 そしてそのような状態を「死の四重奏」(Deadly Quartet)と命名しました。 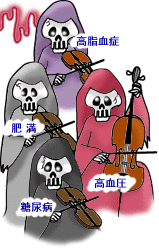 肥満 「死の四重奏」の中でもいちばん最初に現れるのが「肥満」です。 肥満の目安としはBMI値がひろく用いられています。 体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)として求めた数値が18.5~25未満であれば「普通体重」。 標準はBMI値が22の状態といわれており、25以上なら「肥満」です。 肥満にも「リンゴ型」と「洋ナシ形」の2種類があります。 「リンゴ型」は腹部の内臓周囲に脂肪が付く、内蔵脂肪型肥満。 「洋ナシ形」はヒップやふとももに脂肪が付く、下半身太り型肥満。 生活習慣病にかかわりが深いのは、リンゴ型の方で、どちらかといえば男性に多い肥満と言われています。 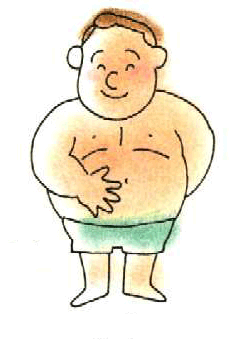 リンゴ型肥満
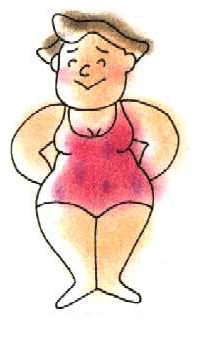 洋ナシ型肥満
高血糖私たちが食事で摂取した糖質は、ブドウ糖として小腸で吸収され、体の各部でエネルギーとして活用されます。 ブドウ糖を体の細胞に取り込むには膵臓から出るインシュリンというホルモンが必要ですが、このインシュリンの働きが悪くなったり、量が不足したりして、ブドウ糖が細胞に取り込まれずに血液中に多く残ってしまう状態を高血糖といいます。 高血糖が長く続けば「糖尿病」になってしまい、合併症の危険性も高まります。 高血圧 高血糖で体内のインシュリン濃度が高い状態(高インシュリン血症)が続くと、自律神経の交感神経にスイッチが入りっぱなしとなり、体は常に緊張状態となってしまいます。 その結果、血管が収縮、血圧が上がってしまいます。 肥満者の高血圧症の発生率は、標準体重を維持している人の4~5倍とも言われ太っていること自体が心臓に負担をかける原因となります。 さらに体内にたまった塩分も排泄されにくくなり、さらに肉体的・精神的ストレスが加わることで血圧が上昇しやすくなってしまいます。 高脂血症 最近よく言われるサラサラ血とドロドロ血。高脂血とはまさにこのドロドロ血のことです。 この高脂血の状態が長く続くと、高脂血症というれっきとした病気になってしまいます。 血液中のコレステロール・中性脂肪などが多いと、赤血球や白血球が柔軟性を失なってしまい、くっつきあったりしてサラサラとは流れられません。 血流が緩やかになったり少し血管が狭くなっているだけでも色々なトラブルが発生してしまいます。 これらの4つの病態がどうして同じ人に多発するのか、その理由は現在でもよく分かっていませんが、中心となるのは内臓への脂肪蓄積(上半身肥満)と考えられています。 すなわち、何らかの体質がある人が、過食、運動不足などの生活習慣になると、内臓への脂肪の蓄積が起こります。 内臓への脂肪の蓄積は、膵臓から分泌されるインスリンのはたらきを弱め(インスリン抵抗性ともいう)、耐糖能異常や高トリクリセリド血症を引き起こします。 一方、インスリンの作用が低下すると、それを補おうとしてインスリンが過剰に分泌されることになり、高インスリン血症の悪化という悪循環を形成しながら高血圧を引き起こすと考えられています。 四重奏4つ全部が1人の人に揃うことは少なく、いくつかがいろいろな組み合わせで出現するのが普通です。 これらの事から「死の四重奏」は、別名「インスリン抵抗性症候群」や「内臓肥満症候群」とも称されます。 あなたの耳に「死の四重奏」が聞えてこないために、生活習慣の修正に努力しましょう。 【平成17年7月 補足】 平成17年4月に内科学会を中心とした8学会が共同で「メタボリックシンドローム」の診断基準を発表しました。内容は「死の四重奏」とかなり近似していますが、新しい提案ですので別項目としてまとめてみました。こちらも参照してみてください。 |
 死の四重奏
死の四重奏