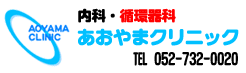
動脈硬化や血栓などで心臓の血管が狭くなり、血液の流れが悪くなると、心臓の筋肉に必要な酸素や栄養がいきわたりにくくなります。 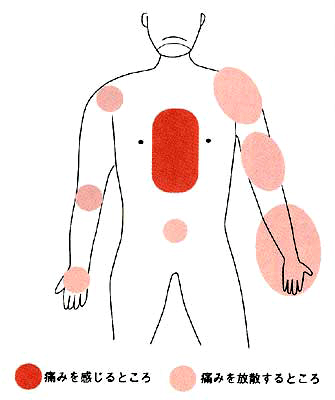 心臓の働き 心臓は心筋と呼ばれる筋肉からできており、血液を全身に送り出すポンプの働きをしています。血液は体をまわりながら酸素や栄養を運ぶ役目をしています。 冠動脈の働き 心臓自身も働くためには酸素や栄養素が必要です。それらを心臓の筋肉へ運ぶ血管が冠状動脈です。心臓を養っている冠状動脈には、太い3本の枝(左冠動脈前下行枝、左冠動脈回旋枝、右冠動脈)があり、心臓の回りを王冠のようにめぐっています。 狭心症と心筋梗塞 動脈硬化や血栓(血管の中にできる血の塊)などで心臓の血管が狭くなり、運動や強いストレスがかかった時に、主に前胸部、時に左腕や背中に痛み、圧迫感を生じるのが狭心症です。安静にしたり、ニトログリセリンの舌下などで血液不足が改善されると痛みが消失します。痛みの持続時間は数分前後で、ニトログリセリンが良く効きます。 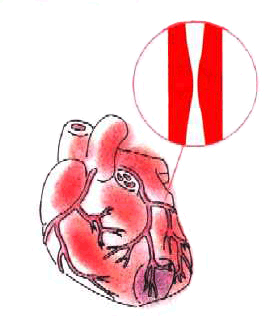 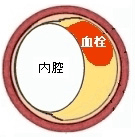 狭心症の人の冠動脈
心筋梗塞は、冠状動脈が完全につまってしまい、心臓の筋肉に酸素と栄養がいかなくなり、その部分の壁の動きが悪くなってしまう病気です。心臓の動きが悪くなると、ポンプとしての力が落ちてしまいます。症状としては、激しい胸の痛み、呼吸困難、冷汗、嘔気、嘔吐など、狭心症に似ていますがより重症感があり、さらに痛みの持続時間も長く、ニトログリセンも有効ではありません。ただ狭心症と見分けがつきにくい場合もあります。 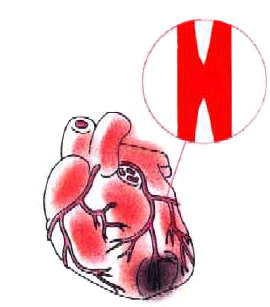  心筋梗塞の人の冠動脈
狭心症と心筋梗塞の違いを簡単に示すと、 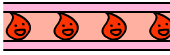 正常状態
 詰まりかけ!
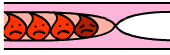 詰まってしまった!
こんな感じになります。「詰まりかけ!」が狭心症で、その場所が完全に詰まってしまえば心筋梗塞です。 心筋梗塞になったら 心筋梗塞を起こした直後は心臓の筋肉が豆腐のようにもろくなってしまいます。このもろくなった部分は日がたつにつれて少しずつ固まっていきますが、完全に固まるのには3ヶ月程度かかります。心筋梗塞になった後の約1週間は、このもろい部分が破れないように安静にしていることが大切です。 心臓のもろくなってしまった部分の筋肉は、動かなくなります。動かなくなった部分の大きさにもよりますが、健康なときに比べると心臓の動きは弱くなっています。そのためにも、心筋梗塞になった直後はできるだけ安静にして、心臓に過度の負担をかけないようにすることが大切です。 虚血性心疾患の合併症 いろいろな合併症が起こります。 ・不整脈 脈がとんだり乱れたり一時的に脈が遅くなります。 ・心不全 心臓のポンプの働きが弱くなり、必要なだけの血液を送り出せなくなります。 血圧が下がったり、息が苦しくなったり、むくみが出たりします。 虚血性心疾患の危険因子 ・高血圧 ・高脂血症 ・糖尿病 ・肥満 ・喫煙 ・精神的ストレス などがあります 狭心症発作時の対処 すぐに医者からいわれている(ニトログリセリンなどの)舌下錠を舌の下に入れてとかして下さい。 1~2分のうちで効果が現れ痛みがとまり胸が楽になります。 5分してもおさまらない時はもう1錠使って下さい。 ただし、血圧を下げるおそれがありますので、1回の発作では3錠までにしておいて下さい。 狭心症の発作が起きた時は安静にするのが第一です。 できれば静かに横になり衣服をゆるめて保温に気を付けます。 いつ、どんな時に痛くなるかも知れません。 外出するときは常に舌下錠を携帯しておきましょう。 ただし、次のような時にはすぐに受診しましょう。 今までにないひどい痛みの時 薬を舌下しても30分以上痛みが続く時 胸痛の回数が以前より増えてきた時 安静時にも痛みが起こる場合 受診する際には、「いつ」「何をしている時に」「どれくらいの痛みがおき」「薬の効果がどうだったか」覚えておくことが大切です。 そのためにも胸痛の記録をつけておくと良いでしょう。 (ニトロ製剤の正しい使い方も参考にして下さい。) 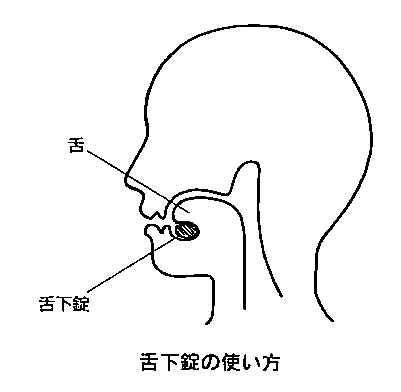 -注意- 発作時に使用する薬剤は、病状によって各自異なります。使用薬剤は、主治医により処方をうけられ、使用方法や注意事項について、あらかじめ確認しておくようにしましょう。 日常生活の留意点について 1.運動 一度つまってしまった血管は、元には戻りませんが、少しずつ運動することにより、つまった血管の代わりとなる新しい血管ができてきます。そのためにも、運動療法は必要です。 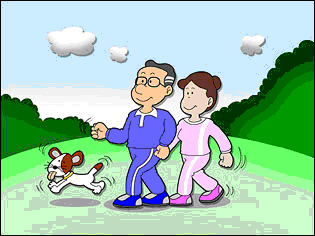 2.二重負荷 心臓への負荷を少なくしましょう。 食事をとる、排便をする、入浴をする、運動をするなどは一つ一つの動作だけでも心臓に負担をかけます。これらの動作をたて続けに行うと、心臓に大きく負担をかけ、発作の起こりやすい状態になります。これを二重負荷といいます。一つの動作を行った後は30分程休んで、その後次の動作を行うようにし、二重負荷を避けましょう。 また、薬を飲む前後は薬の効果が十分に現れていない時です。この時も、発作が起こりやすい状態になっています。薬を飲む前後1~2時間は、動いたりせず安静にしていましょう。 3.便通について 便をする時にいきみ過ぎると、血圧を上昇させ、心臓に負担をかけます。 便通をよくするために、便意があるなしに関わらず時間を決めてトイレに行く習慣をつける。 朝、起きたらコップ一杯の水や牛乳を飲む。 (冷水は発作を誘発するおそれがあるので避けた方ががいいでしょう。) おなかのマッサージをする。 繊維の多い野菜をとる。 効果のない時は、医師に相談して便秘の薬を出してもらいましょう。寒い夜トイレに行く時は、暖かくして下さい。 4.入浴について お湯は、39~40℃位のぬるめにし、長湯をしないようにしましょう。 また、寒暖の差を考慮して、脱衣所も含めて風呂場を暖めて入りましょう。また、湯冷めしないよう気を付けましょう。 5.たばこ たばこは、この際ぜひやめましょう。 たばこが動脈硬化を招くことが確かめられています。また心臓の血管を収縮させ、血圧を上げることもあり、心臓に負担がかかります。 6.コーヒー、紅茶、緑茶 これらにはカフェインが入っているため心臓を興奮させる働きがあります。 しかし、適量は心身をリラックスさせる働きもありますので飲み過ぎないようにすれば飲んでもかまいません。 7.夫婦生活について 性生活は、一般的に一時的な急激な運動と同等に考えられます。 胸痛・息切れ・動悸を感じない程度にしましょう。同上の症状が、性交の間や直後持続するようであれば、出来るだけ早く医師に相談して下さい。ほとんどの場合、負荷となる行為をやめると不快感はおさまります。 また、最近話題の勃起不全治療薬クエン酸シルデナフィル(バイアグラ)、塩酸バルデナフィル(レビトラ)は絶体に使用しないで下さい。禁忌です。 詳しくは医師にご相談下さい。 8.食事について 日々の生活の糧となる食事は、循環器とも密接なかかわりを持っています。 このかかわりを知り、バランスのとれた食事をとることで、症状がおさえられることも少なくありません。 何に注意して、どのようにして食べたら良いのか、基礎知識をきちんと把握して、さっそく実践してみましょう。 |
 虚血性心疾患
虚血性心疾患