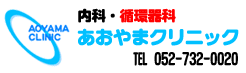
おなじみの「血圧」。でも、そもそも血圧って、何? 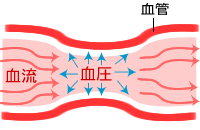 血圧を測ると何がわかる? ひとつは、高血圧の診断や病気の人の心臓機能がどのような状態にあるかということです。高血圧の状態が続くと、脳卒中や心筋梗塞など命に関わる病気につながりかねません。 もうひとつは、動脈の病気の診断です。例えば右と左の眼底血圧値が違っていれば、片側の内頸動脈閉塞が診断できるし、上腕動脈圧や股動脈圧が右側と左側で違っていれば、大動脈の閉塞性の病気の診断ができます。 血圧が上下するのはなぜ? 「そんなに怒ると、血圧があがっちゃうよ!」なんて言いますが、これって本当なんです。 血圧は、心臓から押し出される血液量(心拍出量)と、血液に対する抵抗(血管抵抗)によって決まります。 つまり血圧は、心拍出量が増えたり、心臓の拍動が強くなったり、心拍数が上がったり、血管が細くなったりすることで、高くなると考えられます。 日常生活で血圧が上がるシーンといえば、お風呂に入ったり、運動したときが考えられますが、カッカと怒っているときや、緊張したりストレスを感じている場合も血圧が上がっています。精神的ストレスなどで大脳が興奮すると、延髄にある心血管中枢にその興奮が伝わり、心拍出量が増え、血管抵抗が高まり、その結果、血圧は上昇するのです。 でも、上がりっぱなしの血圧を下げる機能も、私たちの体にはちゃんと備わっています。大動脈や頸動脈に存在する「血圧センサー(圧受容体)」が血圧上昇を感知すると、心血管中枢へ向かって興奮を抑えるように命令し、血圧は元の値に戻るのです。 急に立ち上がったときには、血圧は一瞬低くなりすぐに圧受容体の作用で元の血圧値が保たれることになります。この調節がちょっと遅れたりするといわゆる立ちくらみのような症状が出現してきます。 また、血圧は夜間に低下し変動の幅も小さくなります。これは、自律神経、特に交感神経系の活動が低下するためと考えられています。 血圧の値が2つあるのは何故? 一度でも血圧を測ったことのある方ならもうご存知ですね。血圧の数値には「上の血圧(最大血圧)」と「下の血圧(最小血圧)」の2つがあります。この2つの血圧の数値は、心臓の動きと関係しています。 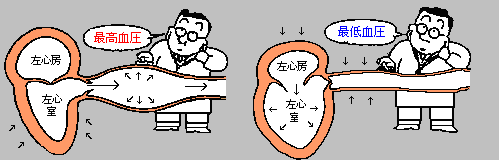 心臓はドックン・ドックンと拡張と収縮を繰り返しながら、休むことなく全身に血液を送り続けています。心臓の収縮に関連して発生した圧力の最大値を一般に「収縮期血圧」と呼んでいます。 一方「下の血圧」は、全身を回って戻ってきた血液を心臓に取り込むときの動脈の内圧のことで、正確には「拡張期血圧」と言います。血圧値が正常かどうかを診断する際、この2つの数値が合わせて診断されるのです。 高血圧の9割近くが原因不明 「高血圧」とひとくちに言っても、実は2種類あることをご存知ですか? 原因がはっきりわかっていない本態性高血圧症と、原因がはっきりしている二次性高血圧です。意外にも、日本人の高血圧症の9割近くは、本態性高血圧症なのです。 本態性高血圧症の初期は、循環血流量が増えているだけで血管抵抗は健康者と変わりないのですが、本態性高血圧症という状態がほぼ完成した時期では、増加した血流量はまた普通の状態にもどっていて、いつのまにか血管抵抗が異常に高くなっているのです。 前世紀の学者が半世紀もかかって研究しているのに、本当の原因はまだ解明されていません。現在では、「本態性高血圧とは、遺伝や様々な環境因子で発生する病気」と解釈されています。 一方、二次性高血圧の原因は、腎臓、内分泌系、血管や心臓、脳や中枢神経などの病気が原因と考えられています。比較的若い人に多く、両親や近い親戚に本態性高血圧の人がいなかったり、降圧剤を飲んでも血圧が下がりにくいといったケースに多く見られます。 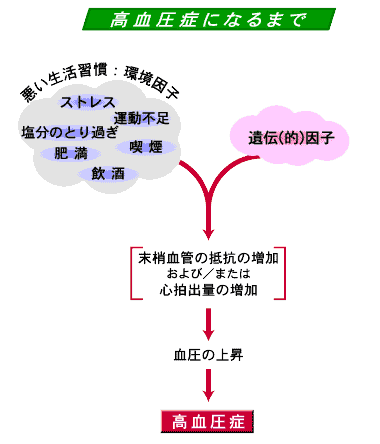 高血圧の検査 1回や2回の血圧測定で高血圧だったとしても、それだけでは本当の高血圧症と決めつけるわけにはいきません。血圧が高い場合には、まず詳しい問診や診察と血圧測定の繰り返しによって、ふだんの血圧も高いのかどうか(ほんとうに高血圧かどうか)をチェックする必要があります。 また、一日の中での血圧変動についても注意深く見なければなりませんが、この場合には必要に応じて24時間携帯型血圧測定装置(ABPM)を用いることになります。ちょうど、不整脈の時に行われる24時間心電図の血圧版と理解していただけばよいかと思います。 それと同時に高血圧症であるなら、それが本態性高血圧症なのか、二次性高血圧症なのかの鑑別も重要です。この鑑別には血液検査や尿検査が必要になりますが、内容がやや特殊になるので結果が出るまでに少し時間がかかります。 治療の原則 高血圧症の治療では、降圧剤を使って積極的に血圧を下げる場合と、降圧剤を使わずに食事や暮らしの工夫だけで血圧を下げる場合とがあります。降圧剤を使うのは、血圧値がある程度高く一般療法だけでは効果がないと判断された場合です。 もちろんその場合も、食塩制限や肥満解消、運動訓練といった一般療法は必要です。 減塩で高血圧を予防
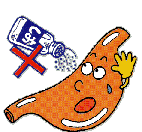 降圧剤の使い方 現在使われている降圧剤は数多くあり、血圧を下げるしくみも作用も千差万別。同一薬剤でも何種類もの働きを持つものがあり、また心臓や腎臓機能に対する作用もまちまちです。 もともと血圧を下げる目的は、脳卒中や心筋梗塞、尿毒症などの合併症防止にあるのですから、血圧は下がったけれども腎臓機能が低下したというのでは意味がありません。特に原因のはっきりしない本態性高血圧症の場合は、血圧値だけではなく、心臓や腎臓に障害があらわれていないか、眼底はどうかなど、必要な検査を含めた慎重な診察によって、その人にいちばん適している降圧剤を選ぶ必要があります。 医学や薬学の進歩によって、最近では降圧剤の種類が増えてきました。もともと高血圧治療は、長期にわたって続ける必要があり、1種類の降圧剤だけで十分な降圧を得ようとして量を増やすと長い間には副作用が出てくるおそれがあります。少量で効かない場合は、量を増やすのではなく、降圧の作用が違う他の降圧剤と併用して降圧効果を大きくしていくのが良策です。「医者は薬をたくさん使いすぎる」という批判がありますが、正しい降圧剤治療というものは、二種類以上の薬をうまく組み合わせて使うのが常套手段です。薬の服用にあたっては担当の医師とよく相談し、不安を解消するようにしてください。  |
 血圧ってなに?
血圧ってなに?