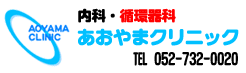
肥満は本来体脂肪の異常増加を意味し、通常は体重で定義されます。 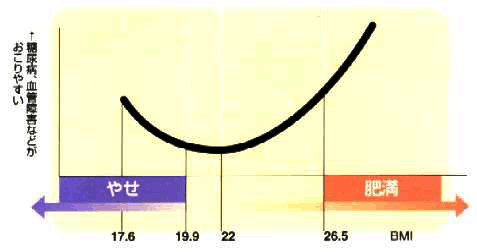 肥満は健康に悪いのでしょうか? 肥満は糖尿病、高血圧、高脂血症、動脈硬化症や胆石症、呼吸異常、腰痛、変形性膝関節症などをもたらし、肥満とともに死亡率が増加します。 肥満のうちこれらの合併症を持つ、あるいは将来これらの合併症をきたす可能性があるものを肥満症と呼び、治療対象と考えます。 体重だけでなく、体型、スタイルについてはどうでしょう? 体型(脂肪蓄積部位)は大変重要です。上半身型(リンゴ型、腹部)肥満の方が、下半身型(洋なし型、ヒップ)肥満より合併症が多いことが知られています。どちらの体型であるかはウェスト・ヒップ比(ウエスト÷ヒップ)を求めることで判ります。男性は0.9以上、女性で0.8以上になると要注意です。 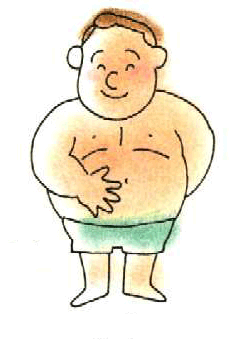 リンゴ型(主に内臓脂肪)
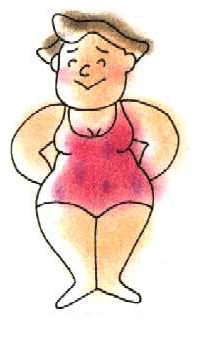 洋なし型(主に皮下脂肪)
どうして肥満になるのですか? 食事などで摂取するカロリーが、消費するカロリーより多い場合肥満になります。言い換えれば、食べすぎ、あるいは運動不足が肥満の原因です。この食べ過ぎや運動不足は遺伝的素因(体質)と環境因子(生活習慣)がもとでおこります。 消化器系の吸収能力にも個人差があり、摂取したものほとんどすべてを吸収する人もあれば、どれだけ食べても体に付かない人もあります。 また、肥満していない人は脂肪の蓄積量により食欲がうまくコントロールされます。 脂肪を蓄積する細胞である脂肪細胞から食欲抑制ホルモン(レプチン)が分泌されているのです。肥満者ではこの食欲抑制ホルモンがうまく働かなくなっているのです。 肥満の人は消費エネルギーより摂取エネルギーが多い。 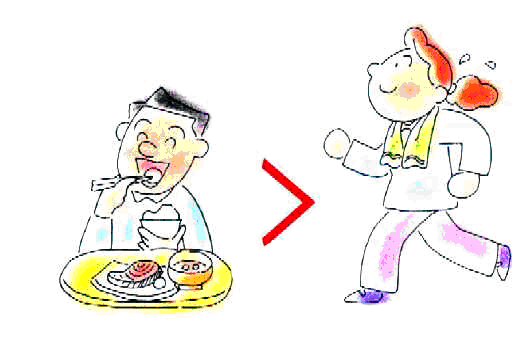 摂取エネルギー 消費エネルギー
肥満症の治療は? まず、長く続けて行うことが最も重要です。1kgの減量には7000kcal消費する必要があります。 例えば、3kgの減量のためには 21,000kcal の消費が必要ですので、仮に30日間で3kgやせるためには1日700kcal消費しなければなりません。 1.食事の制限:標準体重×20~25kcalに制限します。 特に脂肪を制限するとより効果的ですが、良質の蛋白質の摂取も必要です。 2.食習慣改善:まとめ食い(朝食抜き)、ながら食い、早食い、やけ食い、気晴らし食いや夜食、間食などは、やめて、ゆっくりよくかんで食事を楽しむようにしましょう。 3.運動療法:中程度の運動(壮年者では1分間の脈拍が120程度になるような運動)を毎日最低30分おこなうとよいでしょう。 血糖、脂質、血圧にも好影響をもたらします。 ただ、行う前に主治医にご相談ください。 4.薬物療法:食欲抑制剤 カロリー制限開始時に補助的に短期間使用することがあります。 しかしながら、薬剤の特性や処方上の制約から基本的にはあまり使用したくない薬剤です。 これらを実行するには強い意志が必要でしょうね。 最後に、地球上の他地域では、いまだに飢餓が深刻な問題となっていることも忘れずにいてください。  |
 肥満とは?
肥満とは?