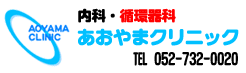
日本人は入浴好きと言われており、清潔、保温、疲労回復などの効用があります。  一方、高血圧・心臓病などの方は入浴の仕方によってはかなり危険を伴います。 入浴関連の死亡事故は1年間に15,000人とも言われており、これに加え致命的とまではいかない入浴関連での事故は相当な数にのぼると推定されます。 また季節でみると冬期に特に多くなる傾向があり、気温の影響も見逃せません。 入浴死の主因は心筋梗塞と脳卒中 入浴死の原因の過半数が心筋梗塞で、次が脳出血・脳梗塞等の脳卒中です。 これらは血圧上昇による血管へのストレスや、体温上昇により血液がかたまりやすくなり、心臓や脳の動脈に血栓を生じることが原因と言われています。 血圧上昇の影響 特に脱衣室や浴室の温度が低い場合、寒さのため血管が収縮し血圧が上昇します。 また高温のお風呂では交感神経が緊張して血圧上昇と脈拍増加が現われます。 冬はシャワーでお湯をはったり、風呂の蓋をしない、シャワーを浴室内に撒くなどにより浴室の温度を上げるようにしましょう。 また高齢者では浴室温度が低く、お湯の温度が高くなりがちな一番湯は避けましょう。 特に高血圧の方は寒冷や交感神経緊張による血圧上昇の割合が大きく危険です。 動脈硬化を生じている血管は血圧上昇に耐え切れず血管が破れることがあり脳出血の原因となります。 また動脈硬化で不安定な脂肪班を生じているような場合、急激な血圧変動により不安定なプラークにストレスがかかり、プラークが破れることで2次的に血栓を形成して血管をつまらせる心筋梗塞や脳梗塞を生じる危険が高まります。 水圧の影響 心不全など心臓の機能が低下した心臓病の方では、入浴による水圧の影響も見逃せません。 家庭の風呂では体に500Kg前後の水圧がかかるとされており、心臓に戻る血液量が一気に増し、心臓への負荷も生じますので、みぞおちの高さの半身浴がおすすめです。 寒く感じる場合は、タオルを肩にかけ冷えないようにしましょう。  体温の上昇の影響 入浴により体温が上昇すると ・末梢血管が拡張して、血圧が低下し、血流がゆっくりとなる。 ・発汗により血液が濃縮される。 ・体温が2度以上上昇すると動脈血栓の原因である血小板同士がくっつきやすくなり、血栓を生じやすくなる。 ・出来た血栓を溶かす働きも低下する。 などの理由により心筋梗塞や脳梗塞がおきやすくなります。 特に、既に動脈硬化により心臓や脳の血管が狭くなっている場合には要注意です。 実際に入浴死の際のお湯の温度を調査した報告では41℃以上での事故が多いとの傾向が明らかであり、高齢者や高血圧・心臓病の方は高温のお風呂を避け38℃から40℃で5分から7分前後の入浴が賢明です。 もちろん食直後・飲酒後は血圧が更に低下し血液の流れが悪くなりますので入浴は避けましょう。 また最近の東京消防庁の調査では、高齢者の入浴死の新たな原因として体温上昇と血圧低下による一種の熱中症が意識障害の引き金になるとの報告もされていますので、湯温は低めに、入浴時間は短めが安全です。 入浴方法のまとめ ・ 入浴前後にコップ一杯の水分補給。 ・ 冬期間は脱衣室、浴室をよく温めておく。 ・ 風呂の温度は38℃から40℃。 (乳児の入浴を目安に) ・ 入浴時間は5分から7分程度。 ・ 半身浴が心臓に負担がかからない。 ・ 浴槽から急に立ち上がるのはさける。 以上を守って快適で安全な入浴を楽しみましょう。 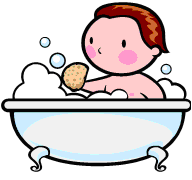 |
 入浴死は意外と多い!
入浴死は意外と多い!