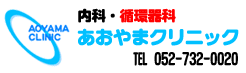
脳卒中は依然として死因の上位を占めていて、がんや心臓病と共にいわゆる3大成人病として関心が持たれています。 脳卒中の種類 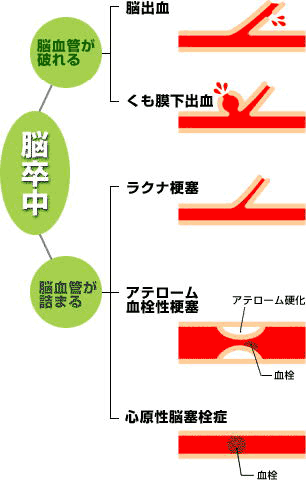 脳卒中は、脳内の血管が破れる(1)脳出血・(2)くも膜下出血と、 脳内の血管が詰まってしまう(3)脳梗塞・(4)心原性塞栓症、 さらに脳梗塞の前駆症状といわれる(5)一過性脳虚血発作や、 不安定な高血圧患者さんが発症する(6)高血圧性脳症の6つに分類されます。 (1)脳出血 脳の血管が、動脈硬化によって脆くなっているときに血圧が高くなると動脈が急に破れて脳の中で出血が起こります。脳出血は多くの場合、突然意識を失って倒れ、深い昏睡に陥り半身マヒを起こします。 (2)くも膜下出血 脳は、脳軟膜、くも膜、脳硬膜という3層の膜に覆われていて、脳頭蓋骨によって守られています。くも膜と脳軟膜の間には細い血管が通っていますが、この血管に動脈瘤や動脈硬化があると、血圧が高くなったときに突然破れます。 これをくも膜下出血と言います。何のまえぶれもなく突然激しい頭痛に襲われ、一時的に意識を失ったり、昏睡状態に陥ります。 イメージが湧きにくいと思いますが下図を参考にして下さい。 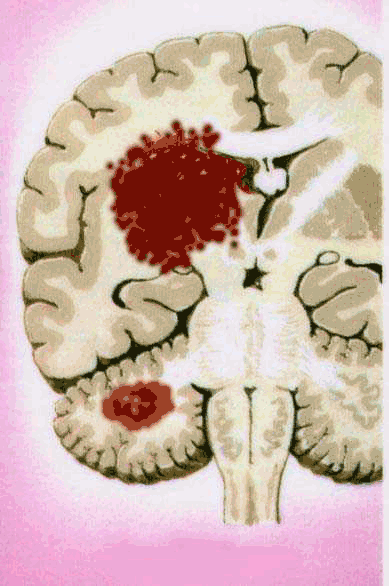 脳出血
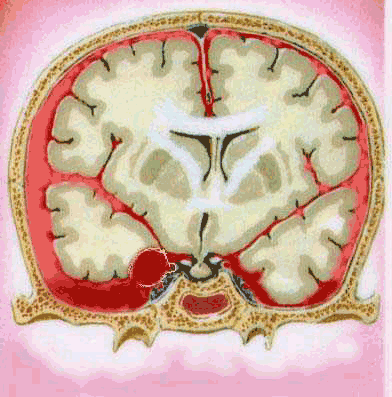 クモ膜下出血
(3)脳梗塞 脳の血管が動脈硬化を起こして細くなり、血流が途絶える場合を脳血栓といい、心臓で出来た血液のかたまりが、脳の血管につまる場合を脳塞栓といいます。脳血栓は、主に高齢者に起こり、知覚障害、運動障害、意識障害などが徐々に進行します。脳塞栓は、突然に半身のマヒや言語の障害によって始まることが多いものです。血流が途絶えた部分の脳細胞は死んでしまい、元に戻ることはありません。 脳内の非常に細い血管におきるラクナー梗塞と、比較的太い血管におきるアテローム血栓性梗塞とがあります。 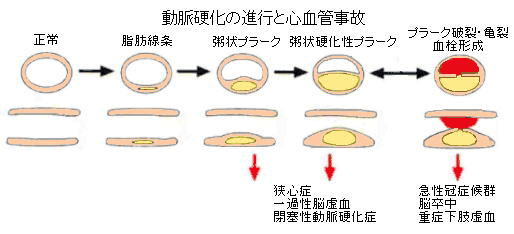 (4)心原性塞栓症 不整脈などで心臓にできた血栓が何かの拍子に突然はがれ、心臓から血流に乗って脳内の血管に流れ込んで血管を閉塞させてしまう状態。 通常の脳梗塞に比べて、発症がさらに急激であるという特徴を持つ事や、不整脈の患者さんの中で最も頻度が高いとされる「心房細動」から正常の脈拍に戻るときに多く発生するため、「動悸が収まったらマヒが出現した」事例が多いのも特徴として挙げられます。 最近では、元プロ野球監督で野球のオリンピック日本代表監督がおこしたのも心原性脳梗塞で、一時新聞記事によくこの病名が載りましたのでご記憶の方も多数みえると思います。 (5)一過性脳虚血 動脈硬化のために一時的に起こる脳の循環障害で、普通は数分間長くても1時間以内に消えてしまいます。一過性脳虚血は脳卒中の中でも脳血栓のまえぶれといわれ、早期に治療を始めることで、脳血栓の進行をくいとめることが可能な場合もあり、すぐに医師の診療を受けることが大切です。 下図で詰まりかけ状態が一過性脳虚血発作、詰まってしまうと完全な脳梗塞になります。 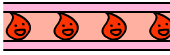 正常状態
 詰まりかけ!
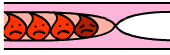 詰まってしまった!
次のような症状は、一過性脳虚血が起きたときによくみられます。 手足の障害: 片側の手足がしびれる、足に力が入らない、箸がうまく使えない、字が書けないなど。 言語障害 : 口が利けなくなる、舌がもつれるなど。 これらの症状は、いずれも一時的に現れるものですが、治っても安心してはなりません。 この他にもバランスがくずれてよろけやすい、忘れっぽいなどの症状が出たらすぐに医師の診察を受けましょう。 (6)高血圧性脳症 高血圧がひどくなり、脳の内部にむくみが起こる事によって発症する。 頭痛、嘔吐、手足のけいれんなどが主な症状であることが多い。 血圧が下がることで自然に症状は消失するが、ひどくなると失明の危険もあります。 脳卒中の症状は? 脳卒中の症状は、みなさんよくご存じの半身マヒの他にも、失認・失語・半盲や、構語障害・嚥下障害、さらには膀胱・直腸障害などまさに十人十色です。 具体的に表現すると、片方の手足が動きにくい、しびれ、脱力感、頭痛、物が二重に見える、視野が狭くなる、呂律が回らない、物が飲み込みにくい、言葉が話せない、又は理解できない、などが症状としてあげられます。 ひどい場合は意識が無くなったり、呼吸が止まったりすることもあります。 脳卒中が起こったら (1)楽な姿勢で静かに寝かしましょう。 発作を起こした場所から、静かな暖かい場所に移す。 頭や全身が水平になるようにして、数人で静かに運ぶ。 衣類やネクタイを緩め、嘔吐してものどがつまらないように顔を横に向ける。 呼びかけても反応がない、嘔吐を繰り返す、呼吸が不規則、血圧や体温が下がっている、顔面蒼白などの症状時は動かさないで(2)へ。 (2)呼吸を楽にしてあげましょう。 いびきをかいたり嘔吐をする場合、顔を横向きにします。 入れ歯は外し、吐いたものは棒などにガーゼやタオルを巻いてかきだしましょう。 予防策 1.食事について 日々の生活の糧となる食事は、循環器とも密接なかかわりを持っています。 このかかわりを知り、バランスのとれた食事をとることで、症状がおさえられることも少なくありません。 何に注意して、どのようにして食べたら良いのか、基礎知識をきちんと把握して、さっそく実践してみましょう。 2.日常生活の留意点について (1)脳卒中は動脈硬化が原因となることが多いため、その進行をくい止めることが重要となります。 動脈硬化を進行させる因子は日常生活の積み重ねに左右されるものばかりです。 つまり脳卒中を含めて動脈硬化の予防は日頃の日常生活管理をすることといえます。 (2)最も大事なことは高血圧の管理。 収縮期血圧160mmHg以上の患者さんは3.46倍、拡張期血圧95mmHg以上では3.18倍脳卒中を発症します 。 血圧の薬も、十人十色。定期的な内服に心掛けて下さい。 (3)次に重要なのは糖尿病。 糖尿病があると脳卒中は男性で1.8倍~2.18倍、女性も2.17倍~2.2倍多くなります 。 糖尿病の管理はすべての血管病変の基本となります。 (4)脳卒中患者さんの8.2%~9.7% に抗リン脂質抗体が証明されます。 抗リン脂質抗体症候群では脳梗塞の発症率が陰性者の2.31倍~4倍です 。 抗リン脂質抗体症候群の方についてはワーファリンの使用が推奨されています。 (5)最近新聞やテレビで取り上げられ一般に知られるようになってきた睡眠時無呼吸症候群。 太っている方や呼吸器系疾患にかかっておられる方に多く、高血圧や脳卒中の強い危険因子と考えられています。 疑わしい方は簡単な検査で調べることが可能です。 |
 脳卒中
脳卒中