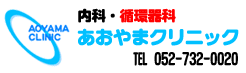
生活習慣病は、以前は「成人病」と呼ばれていましたが、発病の原因が日常生活のさまざまな部分にひそんでいるため、このように呼ばれるようになりました。つまり、成人病が中高年になってから注意すべきというイメージがあったのに対して、生活習慣病は子どもも含めて一生にわたって健康的な生活を心がけ、病気になることを予防すべきものという意味が含まれています。 生活習慣病は「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関与する疾患群」とされ、糖尿病、肥満、高脂血症、高尿酸血症、循環器疾患、大腸癌、高血圧症、肺扁平上皮癌、慢性気管支炎、肺気腫、アルコール性肝障害、歯周病、骨粗髪症などが含まれます。 病気を進行させる生活習慣 長年生活をしていると、その生活習慣・家庭環境・社会環境などの因子が体に悪影響を及ぼしはじめます。それに遺伝的要因がからみ、さらに加齢による老化現象も加わって、いつのまにか私たちの体をむしばんでいきます。 では、病気を発症させ、その進行に影響を及ぼす生活習慣とは何を指すのでしょうか。  食習慣 食習慣 運動不足 運動不足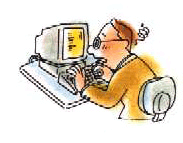 ストレス ストレス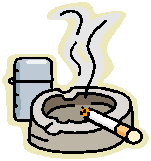 喫 煙 喫 煙 飲 酒 飲 酒この五つが生活習慣病を発症させ進行させていく大きな要因です。つまり、アンバランスな食事の内容と不規則な食事時間、運動不足、ストレス、さらに喫煙と過度な飲酒が、この病気と隣合わせの生活といえます。 生活習慣病は30~40歳代に急増します。しかし近年は発症年齢が低下し、若い人・子どもにもその徴候がみられるようになってきました。これも食生活の変化、運動量の不足などが原因となっています。あなたの生活習慣が病気を進行させていないか、もう一度見直してみましょう。 なぜ生活習慣病が増えているのか? 生活習慣病が増加した背景には、現代の豊かな日常生活が大きく反映しています。 豊かな食生活は食べ過ぎでないにもかかわらず摂取エネルギーが過剰となり、その一方で慢性的な運動不足により消費エネルギーが減少し、この極端なアンバランスが生活習慣病を発症させる要因となっています。また、ストレスの増大も大きく影響していると考えられます。 豊かな食生活 家庭の食卓やファースト・フードなどで出されるハンバーグやカレーライス、スパゲッティーなどは、現代人がよく食べる食事です。戦後の食生活の欧米化は、外食だけではなく家庭にも進出してきました。しかし、これらは高カロリー・高脂肪食(特に動物性脂肪)の代表で、肥満につながるだけでなく、高脂血症や糖尿病などを発症させて動脈硬化を促進、さらには心臓病などを引き起こす原因となります。 しかも、これらの料理は、子どもが好んで食べるものなので、子どもの健康にも大きな影響を与えており、生活習慣病の低年齢化につながっていると言われています。また保存食の多用に伴う塩分のとり過ぎも指摘されており注意が必要です。 運動不足 自動車を中心とした交通機関の発達、労働の機械化、家庭生活の電化など、現代人の暮らしは大変便利になりました。この歩かなくてよい生活・体を動かさなくてよい生活が運動不足を招き、消費エネルギーの低下や身体機能の低下をうながす原因となっています。 ストレスの増大 社会環境が複雑になり、精神的緊張が続く生活は、現代人をストレス状態に陥らせています。ストレスは単なる心身症というだけではなく、生活習慣病をはじめとしたあらゆる病気の引き金にもなります。さらに体の不調感や異常感、また、ストレスの増大にしたがって増える飲酒や喫煙などもあいまって、私たちの健康に大きな影響を与えています。 忍び寄る沈黙の殺入者 自覚症状なしに殺人者が進入 生活習慣病の多くは、全く自覚症状のないまま進行します。高血圧や高脂血症などもその例で、知らない間に動脈硬化が進行し、いきなり心筋梗塞や脳梗塞を引き起こし、時には死にいたることもあるため「サイレントキラー」あるいは「サイレントマーダー(沈黙の殺人者)」とも呼ばれています。 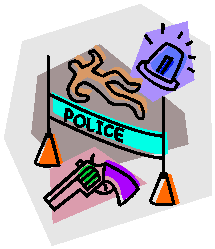 このように、知らず知らずのうちに私たちの体をむしばんでいく生活習慣病の恐ろしさについて十分な知識と意識をもつことが、現代人にとって重要なことです。 生活習慣病予防の第一は定期検診 では、このように自覚症状のない生活習慣病を早期に発見し、また予防するためには、どうしたらよいのでしょう。 それに欠かせないのが定期検診です。検診では、必ず尿検査や血液検査が行われます。これらの検査の数値の結果によって、高脂血症や糖尿病などの早期発見が可能になります。 自覚症状がないため自分は健康なんだと思いこんでいる人に、往々にして定期検診を受診しなかったりする人が見受けられます。しかし、病は静かに進行している可能性もあるのです。定期的な検診で常に健康チェックを行いながら、自分の体を守っていくことを心がけてください。 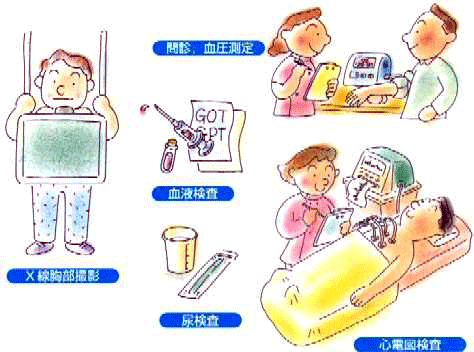 四十歳と生活習慣病 厄年は老化のきざし? 四十歳という年齢は、自分が人生で初めて「もう若くはない」と意識する年頃です。 昔から数え年の四十二歳は男性の大厄といわれ、何かと災難に遭うことが多い年代として注意をうながすため、神社や寺院で厄除けを行う習わしがありました。もちろん厄年はこの年齢だけをいうのではなく、男性では数え年の二十五、六十歳が、女性では数え年の十九、三十三歳(大厄)が厄年にあたります。これらの年齢は、健康面だけではなく、社会的な役割などにおいても、人生の節目、節目の年でもあります。 厄年を契機として生活習慣を点検する 現代でも四十二歳という年齢が厄年としてクローズアップされることが多いようです。 これは、この頃から、高血圧や心臓病などの生活習慣病が体をむしばみ始める年代と重なってくるからです。 しかし、この年代は社会的には重い責任を負わせられる年齢でもあります。会社では中間管理職として多忙な仕事に追われ、家庭では住宅ローンや子どもの教育費など経済的負担をしいられる。肉体は疲労し、ストレスはたまる一方です。また、加齢という現実を避けることはできません。しかし、「もう若くはない」と自覚した瞬間は、これからの健康生活を見直すチャンスでもあるのです。 1.運動不足ではないか? 2.休息はしっかり取れているか? 3.ストレスはうまく解消されているか? 厄年を契機として、自分の生活習慣を点検し、日常の健康管理実践元年の年として位置づけることが大切です。 予防のために生活を改善しよう 生活習慣病を予防するためには、いままでの生活をチェックし、悪いところを改善していく努力が必要です。その重要な要素が「食事・運動・休養」です。 食生活のチェック 高脂血症、糖尿病などの生活習慣病予防の重要なカギをにぎっているのは、食生活です。毎日食べる食事は生活習慣そのもの。その食事が不規則だったり、栄養が偏れば、確実に健康に悪影響を与えます。ここで簡単に生活習慣病予防のための食生活改善のポイントをあげます。 1.一日30食品を目標に! 2.動物性脂肪より植物性脂肪(肉より魚) 3.しょう油、味噌、塩などの調味料の使い過ぎに注意!(塩分は一日10g以下を目安に) 4.甘いものに注意!(砂糖は一日50g以下に) 運動のチェック 運動不足は血液の循環を悪くさせるだけではなく、余剰のエネルギーを蓄積させるため、肥満や動脈硬化をうながします。また、骨や筋肉などの機能も低下させるので、生活習慣病にかかりやすい体をつくってしまいます。 この運動不足を解消するためには、有酸素運動(楽に呼吸ができ、筋肉に十分酸素を送り込める運動)を、主治医と相談しながら生活に取り入れることをお勧めします。 エクササイズウォーキングは、現代人が無理なく生活に取り入れられる運動です。 目指せ一日一万歩! 休養のチェック 最後に何より休息・睡眠を十分とることです。規則正しい生活のリズムが健康生活の第一歩。 そして、節酒・禁煙を心がけることが、あなたの体を生活習慣病から守ることになります。 |
 生活習慣病
生活習慣病