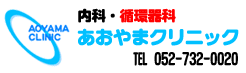
動脈硬化は全身の血管に起こりますが、特に閉塞性動脈硬化症の場合は腹部から下肢の動脈すなわち大動脈下部から大腿動脈の範囲によく見られる血行障害です。 動脈硬化の原因は不明ですが、高脂血症(コレステロール、中性脂肪)が最も重要な関係を持っています。 他に高血圧、喫煙、糖尿病なども大きな因子です。閉塞性動脈硬化症は現在激増しています。 動脈硬化 動脈硬化とは、動脈の内腔にコレステロールやカルシウムが沈着して、動脈壁の一部が硬く、あるいは狭くなったりして血液が通りにくくなるものです。 動脈硬化を起こしている血管は、内腔が狭くなっているため、血液がつまりやすい状態にもなっています。 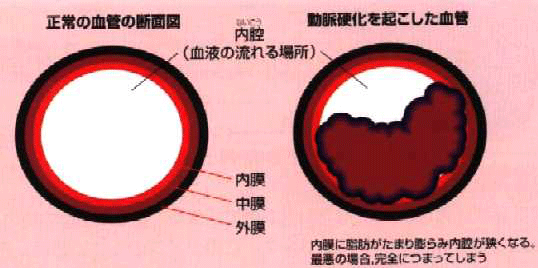 下肢の動脈の解剖について 解剖は結構複雑なので、下図を参照しながら読んでいただくと少しは理解しやすいと思います。 ○腹部大動脈は第4腰椎のレベルで左右の総腸骨動脈に分岐します。 ○総腸骨動脈は骨盤内で内外腸骨動脈に分岐します。 ○外腸骨動脈は下腹壁動脈を分岐した後、大腿動脈となり、膝の直上から下腿動脈を分岐するまでは膝窩動脈と言います。 ○下腿動脈は前脛骨動脈・後脛骨動脈・腓骨動脈以下の3つに分かれ、その後、さらに足部動脈に分岐していきます。 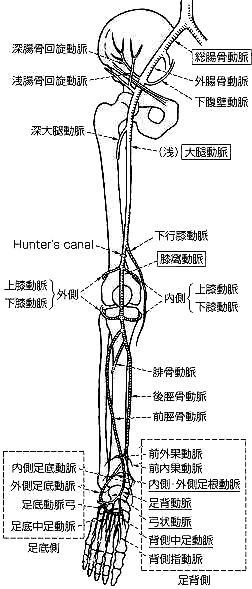 閉塞性動脈硬化症とは 動脈硬化が進行すると、足がいつも冷たかったり、しびれたり、間歇性跛行といって歩くと下腿の筋肉が痛くなるなどの症状がでてきます。 この様な病気を閉塞性動脈硬化症と呼んでいます。 閉塞性動脈硬化症は、全身の動脈硬化の症状のひとつで、他の臓器の血管においても同様に動脈硬化がかなり進行していると考えられます。 閉塞性動脈硬化症の重症度は症状と密接に関係しており、通常は以下に述べるFontaine分類が用いられ、それぞれ治療方法の目安とされています。 閉塞性動脈硬化症の症状 (Fontaine分類) 1期 しびれ・冷感 動脈硬化が原因で足の血行が悪くなり、急激な運動や連続歩行の直後などにしびれ、冷感がみられます。しかしこの段階では血行不全はそれほどひどくなく、多くの場合症状もすぐ消失し、通常は無症状です。また皮膚変化としては皮膚の、皮下脂肪の委縮、脱毛などがみられます。 2期 間歇的跛行期。下肢血行不全の特徴的症状です。間歇的跛行といって一定の距離を歩行した後、特定の筋肉に痛みや硬直を起こして歩行不能になるものの、休憩すると再び歩けるようになります。安静時にはかろうじて血流が保たれていますが、歩行時には足へ十分な血液が供給できなくなって起こる症状です。治療するかどうかは、患者さんの生活状況と不自由さを医師とよく話し合った上で決まります。 3期 安静時疼痛期 もっと血行が悪くなると、安静時にも血液供給が不足するようになります。足を少しでも下げると痛みが軽くなるので、ベットから足を下げて寝るような姿勢をとる人もいます。こうした状態になると足の潰瘍、壊死が起こりやすくなるため、必ず治療する必要があります。 4期 潰瘍、壊死期。小さな傷や圧迫を受けやすい場所、たとえば足趾(そくし)の先端部など血流の悪いところに皮膚の壊死・潰瘍が生じます。血流が悪いために治りが悪く、患部はどんどん広がり、場合によっては足の切断に至ることもあります。すぐに適切な治療を行う必要があります。 閉塞性動脈硬化症の合併症 動脈硬化は全身の疾患なので、閉塞部位によって脳血管障害・虚血性心疾患・腎不全などの合併症を起こす危険性があります。 虚血性心疾患 心臓を養っている冠動脈に起きた動脈硬化のため心臓の一部に血液が十分いきわたらなくなるために起こる疾患です。症状は主に胸に強い痛みを感じます。 脳血管障害 脳に入り込む動脈の動脈硬化のために脳の一部に血液が十分に流れなくなって起こる病気です。言葉がうまくしゃべれなくなったり、一時的に手足が動かなくなったりします。また、一時的ですが目がみえなくなる場合があります。 腎不全 動脈硬化が腎臓に繋がる血管に起きた結果、腎臓の機能が低下してしまった状態です。早期に適切な治療を行わないと進行性に腎機能が低下してしまいます。 閉塞性動脈硬化症の検査 1.四肢動脈拍動の触知 2.上下肢血圧測定 3.ABI (Ankle Brachial Pressure Index) =上腕動脈最高血圧/足関節部最高血圧 正常ABIは1.0以上。 0.9以下は閉塞性動脈硬化症の疑い。 ABIが0.8以上では症状がないとされ、跛行を示す場合のABIの平均値は0.6程度。 4.CT・MRI(MRA) 5.超音波ドップラー検査 6.動脈造影など 初期患者の日常生活と注意・理学療法 日常生活の管理 1.手足の保温に気をつける。 2.深爪などの外傷を避け、皮膚の手入れをする。 3.長時間の起立や正座、しゃがみ込んだ状態を避ける。 4.快適な温度(23から25℃)を心掛ける。 5.足の温浴(傷がない場合)、清潔を保つのも効果的です。 この様に手足の血管に負担がかからないように注意して、病状や症状が悪化しないようにしましょう。 食事について 1.コレステロールや脂肪分の多い食べ物は控える。 2.減塩 3.標準体重を維持する。 閉塞性動脈硬化症は、高血圧や糖尿病により悪化します。 基礎疾患である高血圧や糖尿病を治すためにも、減塩やバランスの取れた食事を心がけましょう。 危険因子を取り除こう タバコは最大の危険因子です。タバコに含まれている物質の中の主にニコチンと一酸化炭素が動脈硬化を悪化させます。ですから、禁煙を必ず実行するようにしましょう。 高血圧・糖尿病・高脂血症・肥満などは動脈硬化を促進します。まず、喫煙している人は禁煙を実行する事が大切です。それから、食生活を改善し、適度な運動などをして危険因子を取り除く努力をしましょう。  毎日歩きましょう 毎日歩行運動を続けていくと側副血行路(狭窄、閉塞動脈部位をまたぐ血管)が発達します。側副血行路が発達すると血流が改善されますので歩行運動は毎日続けるようにしましょう。寒い日は屋外で行わず、屋内で行いましょう。 歩行訓練は、軽症の人が痛みの生じる歩行距離、歩行時間を測定します。そして、歩ける距離の80%歩行するようにし、数分間痛みが取れるまで休息を取るようにします。この訓練を繰り返すことにより、側副血行路が発達し、足の血流が改善されるようになります。改善されなくて、日常生活に支障をきたす場合は、手術療法の適応も考えます。  治療 薬物療法 内服薬では、抗血小板薬をベースに間歇性跛行や軽傷の虚血性潰瘍例に対して血管拡張作用を有する薬剤や赤血球変形能賦活剤を併用します。注射薬は安静時疼痛や重症の虚血性潰瘍に対して、入院のうえ投与するのが原則です。 非観血的血行再建術 A.血管拡張術・経皮的血管形成術(percutaneous transluminal angioplasty: PTA) 閉塞部が短いものには、手術をしないで血管の中に風船のついた管(カテーテル)を入れ、狭窄、閉塞部でふくらませて血管を拡張します。 B.ステント 風船でふくらませた後に金属性の管を血管の中で拡張させます。 手術 A.血行再建術 1.血栓内膜除去術 閉塞部が太い血管で、短い範囲の時は、血管を切開し、閉塞部の動脈硬化病変(血栓)を取り除きます。動脈切開部は狭くならないよう、患者の静脈をしようして血管を広くします。 2.動脈形成術 主動脈は閉塞しているけれども、筋肉の間を通っている細い血管は開通し、そこを通って末梢へ血流がいっている場合には、その血管を太くして血液の流れをよくします。 3.バイパス手術 閉塞部が長い時は、人工血管や自分の静脈を閉塞部の中枢側と末梢側に移植し、バイパス路を作ります。もっとも多く行われる手術で、大変有効な手術です。 B.交感神経切除術 血行再建術の行えない症例や,症状がFontaine分類3期以上の場合に行われますが、皮膚への血流増加作用が強く,筋肉への血流増加作用は弱いので,間欠性跛行に対する作用は弱い。 |
 閉塞性動脈硬化症
閉塞性動脈硬化症