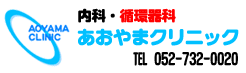
心臓へ戻る血液が逆流しないように、脚の静脈には数cmおきに弁がついています。 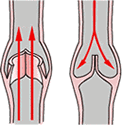 皮膚近くを走る静脈の弁が壊れ、脚のひざから下に血液がとどまり、血管が瘤状に浮き出る病気が静脈瘤です。 女性に多く、痛みやかゆみ・だるさなどの症状が出て、長期にわたる潰瘍が形成される事もあります。 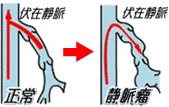 静脈瘤は何故できる? 静脈は、おもに筋肉の圧迫や胸腔内の陰圧を用いて、血液を心臓に環流している。 しかし、動脈と違って血流が緩やかなために停滞しやすく、血流量の増加による静脈内圧の上昇、弁の障害、静脈壁の損傷や血栓などにより逆流や乱流を生じ、静脈瘤が出来ます。 下肢静脈や骨盤内静脈では血栓が生じ、その血栓が剥がれて肺まで到達すると、肺血管の血流を妨げ「肺塞栓症」となります。  伏在静脈瘤
 網目状静脈瘤
なぜ弁が壊れるのですか? 長時間立ったままの仕事を続けるなど、脚の血液が心臓に戻りにくい状況が続くと弁に負担がかかります。長年積み重なると、まず足のつけ近くの弁が機能しなくなり、次にその下にある弁に負担がかかる。そんな風にして弁の故障が脚先の方に向かって進行した結果、少しずつ症状が現れます。妊娠が契機になることもありますが、これは分泌されるホルモンが血管の組織を軟らかくしたり、子宮の重さや出産時の圧力が脚の血液の流れに影響するためと言われています。 保存療法 医療用の弾性ストッキングや弾性包帯で、下肢に適度な圧力を与えることで下肢に余分な血液がたまる事を予防し、本幹の深部静脈への流れを助けます。 薬局やスポーツ店でサポートグッズを扱っていますが、医療施設で扱っているものが効果的です。 現在では、マットな素材から透明感のある素材にかわり、サイズや仕様も選べるようになりました。しかし、あくまでも進行防止・現状維持が目的で、治るわけではありません。 硬化療法とは? ここ10年ほどの間に普及しました。濃い食塩水や界面活性剤などの硬化剤を静脈に注射し、血管の内側の内皮細胞を殺して細胞同士をくっつけて静脈瘤部分の血液の流れを止めます。皮膚を1cmほど切開し、固めたい部分の静脈の上端を糸で縛っておいてから注射するのが確実で、最近の主流です。入院は必要ありません。 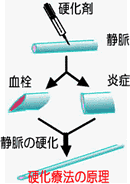 流れ出た血の塊で血管が詰まったりしないか心配ですが? 内皮細胞が死ぬと、血栓が出来ますが、皮膚に近い静脈なら詰まっても問題ありません。 血栓が肺などの血管を詰まらせる可能性はかなり低いのです。硬化療法を受けた人で皮膚に小さなキズ跡があれば、血管を縛っているはずなので、血栓が他の血管を詰まらせることはなく、より安心です。 注意が必要なのは、脚の深い部分の静脈が詰まる深部静脈血栓症の場合です。 患部は摘出できないのですか? 壊れた弁を静脈ごと取り去る手術もあります。ストリッピング手術といって古くから行われています。血管にワイヤを通して先端を固定し、内側に巻き込むようにして抜き取ります。硬化療法が難しい太めの血管にも使える方法ですが、周囲をキズつけやすく、数日は入院が必要です。深部静脈に血栓が無ければ、表面近くの静脈は取っても差し支えありません。 さらに、高位結紮術といって静脈を引き抜くかわりに、弁不全をおこしている静脈と本幹の合流部を縛ったうえで、切り離してしまう治療法もあり、この術式は日帰り外来手術でも可能で、最近では、硬化療法との併用が多く施行されています。 また不全弁を作り直す弁形成術や血管内視鏡による処置を行う施設もあります。 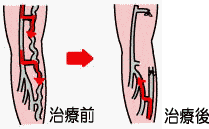 硬化療法後の再発は? 縛った場所以外から血液が流れ込み、数ヶ月で固めたところがはがれることもあります。 再発したら、血管の他の場所を縛ったり、もう一度硬化療法をしたりすることで対処できます。 弁への負担は年々積み重なり、手術をしても、数年後に別の場所に症状が現れることもあります。 命に別状のない良性の病気なので、「一緒に暮らす」というくらいの気持ちでいてほしいと思います。 |
 下肢静脈瘤
下肢静脈瘤