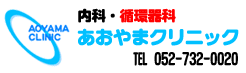
高血圧 塩分の量は、高血圧の方の場合その重症度にもよりますが1日6~8g以下に控えましょう。高血圧のない方でも10g以下が理想的です。食塩に敏感な人では1日の食塩量を3g減らすと、高血圧の人は最大血圧が7mmHg程度、正常血圧の人は5mmHg程度低くなると報告されています。 軽症高血圧の人は減塩だけで血圧をコントロールすることも可能な場合があります。 心不全 心臓病で心臓の機能の悪い方(心不全)も塩分をとりすぎると循環血液量が増え、心臓の負担が増すために息切れやむくみなどを悪化させます。心不全では塩分の量を1日6~8g以下に控えましょう。 腎不全 腎臓の大切な働きの一つに水分や塩分の排泄があります。腎不全と診断された場合、その程度に応じて食事中のタンパク質、塩分、カリウムなどを制限する必要があります。塩分の取りすぎは腎臓の働きをさらに低下させむくみなどの症状や高血圧を悪化させます。塩分制限の程度については医師の指示に従ってください。 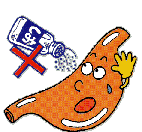 塩分減らして高血圧予防
カリウムと食塩 カリウムは塩分中のナトリウムに対する拮抗作用があります。古くは食塩摂取量の多い同じ東北地方で、秋田県よりも青森県では脳卒中が少ないとの統計がありました。似たような塩分摂取量でも、青森県ではカリウムに富むりんごをたくさん摂るために血圧が低くなることの証明とされています。 すなわちカリウムは食塩による高血圧を抑えます。特に食塩に敏感な人(食塩感受性が高い)ほど効果があります。更に同じ高血圧の方でも低カリウムの人に比較して正常カリウムの人の方が心血管事故が少ないとされています。また、日本人の高血圧の方の半分くらいは食塩感受性があるとされています。 ただし腎臓障害のある方ではカリウムの摂りすぎは危険なこともありますので、主治医にご相談ください。 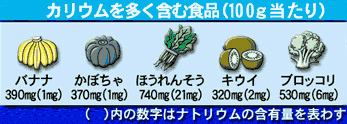 外食における塩分量のめやす 一食の塩分は3g以下が目標とすると、外食で1gからの減塩を目標にしましょう。まず簡単にできるのは、 ・ 汁ものの汁を残す。ラーメンなどの麺類の汁は1/3は残しましょう。 ・ 味噌汁(1杯には塩分約2g)も、具は食べても汁は残しましょう。 ・ 漬物はできるだけ残しましょう。 ・ 料理の味をみてからしょうゆ等の調味料を使用しましょう。 ・ しょうゆやソースなどは、小皿にとって表面だけ味をつけるようにしましょう。(つけ食べ)。 ご飯全体に味のついているものや、どんぶりもの・すしなどは塩分が多く注意が必要です。  寿し(5g)
 ポテトチップス(1%)
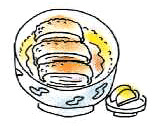 丼物(3g)
 麺類(5g)
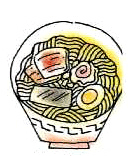 インスタントラーメン(5.5g)
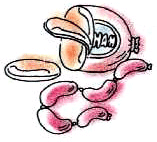 肉加工品
(ハム2枚1.5g、ソーセージ3%)
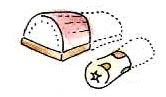 魚加工品
(ちくわ1/2本1.5g、かまぼこ1/2枚2g)
塩分を控えるための調理の工夫 ・ 醤油、化学調味料、だしの素等は出し割り醤油、減塩醤油、減塩ソース等にすると塩分が半分位になります。 ・ ハム・ソーセージ・かまぼこ等の魚肉練り製品は、塩分量が多いので調味料がわりに野菜炒め・チャーハン・野菜のスープ煮・スープ類のだしとして使いましょう。 ・ レモン・酢・カレー粉・わさび・からし・生姜・胡麻を使用して塩分を減らしましょう。 ・ 酸味は食酢以外に、ゆず、すだち、果実酢、トマト、ケチャップ等を料理に合わせて利用します。フライ、焼き魚は、レモン汁などの酸味でおいしく食べられます。 ・ 揚げ物は、表面を油でおおい材料の旨味を逃がさず、また油特有のコクと風味が加わり、塩分の節約ができますが、カロリーには気をつけましょう。 ・ 焼き魚などの焼き物では焦げ目をつけ、焼きたてで食べると塩味のいらないおいしさが得られます。 ・ 香辛料は日本料理ではほとんど仕上げに使い、西洋料理,中国料理では数種類を組み合わせて使います。 ・ 新鮮な素材は薄味でも食材の持ち味を生かすことができます。 ・ 煮物のときは濃いめのだしを使って旨味をプラス。旨味を生かすには塩分控え目の方が効果的です。昆布・かつおぶし・煮干し・干ししいたけ・鶏ガラ・牛のすねなどのだしの旨味を活用しましょう。 |
 減塩の効果
減塩の効果