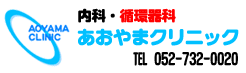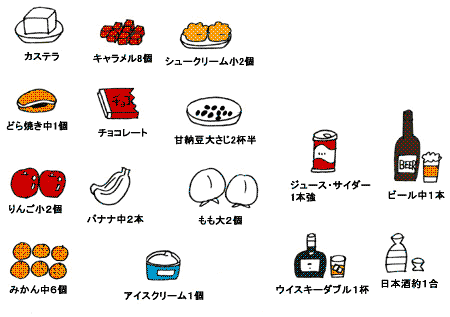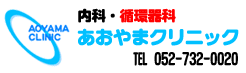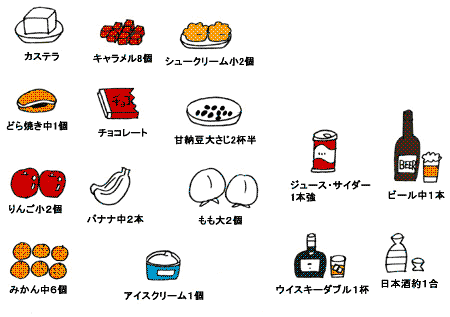| |
 食品交換表について 食品交換表について |
| |
(日本糖尿病学会編/日本糖尿病協会・文光堂発行)
食品についての専門知識がなくても糖尿病・肥満症の食事療法を行いやすくするために、食品交換表というものが作られています。
この表ではバランス良く食べるために食品を6グループに分類しそれぞれのグループを表1、2…6と呼ぶようにしています。
また、ご飯茶わん半分と同じエネルギー量(80kcal)を1単位と決めています。ですから、茶わん軽く1杯のご飯は表1の食品で2単位に相当し、同じ表1の食品2単位分例えば6枚切りの食パン1枚と交換することができます。
表1
主に糖質を含む食品。
穀類、いも、糖質の多い野菜と種実、豆類(大豆は除く)など |
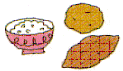
|
表2
くだものです。
表1の食品と同様、糖質が多く、ビタミンミネラル、食物繊維を多く含んでいます。 |

|
表3
主に、タンパク質を多く含む食品。魚、肉、卵、チーズ、大豆製品。 |

|
表4
牛乳、乳製品。カルシウムの供給源として重要。 |

|
表5
主に、脂肪を含む食品。バター、サラダ油、マヨネーズなどの油製品。
少量でも高エネルギーなので、取りすぎには要注意。 |

|
表6
野菜(糖質の多い一部の野菜を除く)、きのこ、海草、こんにゃく。
植物繊維がタップリ! 糖尿病の人にとってはうってつけの食品。 |

|
バランスのよい食品とは?
表1、表3、表6を主体にして、表2、表4を適度に配したものが、バランスのよい食事です。
一単位ってなーに?
「食品交換表」では、体の中で80kcalのエネルギーを生じる食品量を1単位と呼んでいます。
卵1個、白身魚1切れ、豆腐1/3丁、バナナ1本など、日常よく使われる分量が80kcal前後となる食品が多いからです。
食品交換表を見ると同じカロリー(同じ単位数)・同じ栄養価(同じ表)を持つ食品を簡単に探すことができます。
例えば、1日に表1(穀物、いも類など)11単位、表2(くだもの)1単位、表3(魚介類、肉類、卵、チーズ、大豆類)4単位、表4(牛乳・乳製品)1.4単位、表5(油脂、脂身)1単位、表6(野菜、海藻、きのこ)1単位、この他調味料として0.6単位摂取すると、合計20単位つまり1600kcalで栄養のバランス良く食べることができます(例2)。また、同じグループ(表)に入る食品を色々交換することで食品のバラエティを増やすことができます。
栄養のバランスの良い食事例
|
表1 |
表2 |
表3 |
表4 |
表5 |
表6 |
調味料 |
合 計 |
| 食品 |
穀類
いも |
果物 |
魚肉
タマゴ
チーズ
大豆 |
牛乳
乳製品 |
油脂
脂身 |
野菜
海藻
きのこ |
味噌
砂糖 |
|
| 例1 |
6 |
1 |
4 |
1.4 |
1 |
1 |
0.6 |
15単位 |
| 例2 |
11 |
1 |
4 |
1.4 |
1 |
1 |
0.6 |
20単位 |
このように、全体のカロリー量はおもに表1の食品の量で調節できます。
大体のカロリー量を自分で計算する
自宅でも、あるいは外食などでも摂取する大体のカロリー量を自分で計算すると過食の予防になります。
下の図にあるものはすべて160kcal相当の食品です。かるく茶碗1杯程度のごはんに相当しますので、覚えておくと便利でしょう。
|