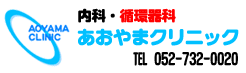
運動は心臓・肺・筋肉の機能強化以外に、肥満の改善、血糖や血圧の低下、HDLコレステロール(善玉コレステロール)の増加効果があり成人病の予防・治療に有効です。 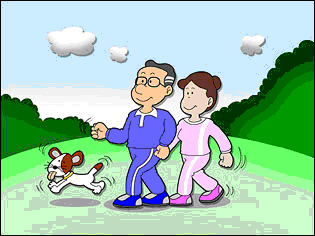 運動療法を行う条件 胸痛、動悸、息切れ、めまい、失神および腰痛、関節痛などがないこと 心臓病、安静時心電図異常、腎臓病、肝臓病などや関節・骨の障害がないこと 糖尿病、高血圧症、高脂血症、肥満症が軽症であることが条件となります。 有酸素運動と無酸素運動 運動と一言で言っても、有酸素運動と無酸素運動の2種類があります。 運動の強さを次第に増し、ある限度を越えると、肺から取り込んだ酸素の供給だけでは追いつかなくなり、無酸素下でエネルギーを作る状態へと変わります。 年齢にもよりますが、脈拍が1分間に110~120を越えると無酸素運動になります。 重量挙げ、懸垂、腕立て伏せ、短距離全力疾走などは、酸素を取り込まずに行われるので無酸素運動と呼ばれ、心臓にも負担をかけるので好ましくありません。また息をとめて力むような運動も極端な血圧の上昇を招き、心臓や血管の負荷になります。 有酸素運動とはウオーキング、サイクリング、水中運動等であり、運動の強さは、自分の能力の5割程度、つまり、軽く汗ばむ程度がよいとされています。 循環器疾患等をお持ちの方は、具体的な運動の程度を主治医にお尋ね下さい。 具体的な運動方法 それまで運動をしていなかった方はいきなり運動療法を始めるのではなく、1~2週間かけて少しずつ体を動かすようにしてください。 また、準備体操、整理体操は十分に行ってください。ストレッチを入念に行うのが効果的です。 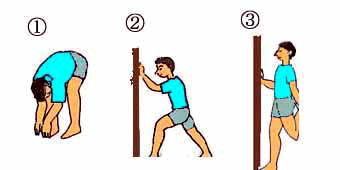 ストレッチ運動の一例
運動療法のため歩行する場合には ・適当な靴(クッション性があり柔らかい) ・吸湿性のよい柔軟性のある生地の服装 ・胸を張り、背筋を伸ばす ・腹を引き締める ・膝、脚を伸ばす ・つま先で地面をける ・着地はかかとから ・歩行はリズミカルに ・歩幅はいつもより広めに などに留意してください。  運動の強さ これ以上は不可能な運動の強さを100%とした場合、成人病の予防・治療のためには40~60%程度の運動が良いと考えられています。なお、当初は30~40%の運動から始めてください。 この運動の強さを測る方法を紹介します。あくまでも無理をしないように心がけてください。 心拍数(脈拍)による判断法 腕時計式の脈拍計も市販されています。
運動の時期と時間 ・ 空腹時・食直後を避け、食後1~2時間に行う。 ・ 一回の運動時間は10分程度からはじめ、 なるべく30分以上行う。 ・ 週に2回以上、なるべく3回以上行う。 ・ 1日に8000歩以上が一応の目安になります。 運動は長く続けて初めて効果がでてきます。糖尿病や肥満症の場合でも、運動療法の目的は、必ずしも毎回の運動で直接ぶどう糖や脂肪を燃やすことではありません。長期的な運動で筋肉量や筋肉を流れる血液の量を増やし、またその他全身の細胞を活性化することでエネルギー消費を円滑にすることが目的です。 長く続けることのできる無理のない運動療法を心がけてください。 |
 糖尿病・肥満症の運動療法
糖尿病・肥満症の運動療法