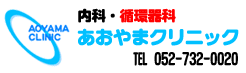
糖尿病とはどういう病気? 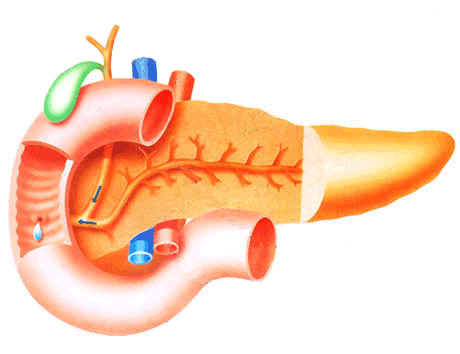 膵臓は胃の裏側にあって見えにくい
2種類の糖尿病 糖尿病には2つのタイプがあります。 1型糖尿病(インスリン依存型糖尿病(IDDM) )は小児や若い人に多く、ウイルスの感染などによりインシュリンを作り分泌する膵臓のランゲルハンス島が破壊され、インシュリンを全く分泌することができなくなり糖尿病になる病気です。 一方、中高年に多い 2型糖尿病(インシュリン非依存型糖尿病(NIDDM) )は日本人の糖尿病のほとんど(約95%)をしめ、インシュリンの分泌量が低下しやすく糖尿病になりやすい体質を持っている人に、食べ過ぎ、運動不足、肥満、ストレス、加齢などのインシュリンの作用を妨害するような引き金が加わって発症します。 糖尿病の患者さんは太っておられる方が多いようですが... 肥満は糖尿病と深く関わっています。調査してみますと、インシュリン非依存型糖尿病患者さんの約2/3が現在肥満であるかあるいは過去に肥満を経験しています。実際、肥満者ではインスリンの血糖低下作用が弱まっていることがわかっています。  肥満するとどうしてインシュリンの作用が弱くなるのですか? 脂肪を蓄積する細胞である脂肪細胞から、インシュリンの作用を妨害する遊離脂肪酸やTNFと呼ばれる物質などが分泌されることがわかっています。 肥満し、脂肪細胞が増え、これらの妨害物質が増えてくると、せっかく分泌されたインシュリンがうまく働くことができなくなり、血糖が上昇するようになります。 糖尿病ではどのような症状が出ますか? 糖尿病の症状としては、無症状のことも多いですが、高血糖によるのどのかわき・多飲・多尿、また細胞のエネルギー不足による体のだるさ・体重減少などがあらわれることもあります。  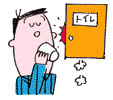  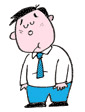  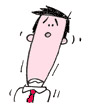 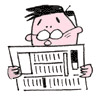 どのような合併症がおきますか? 糖尿病の本当の姿は血管の障害です。 顕微鏡で観察するような非常に細い血管から比較的太い血管まで、全身のあらゆる血管が傷んでいってしまう病気なのです。糖尿病の三大合併症は、網膜症、腎症、神経障害ですが、これらはすべて細い血管に起きた障害の結果なのです。このほかに比較的太い血管の障害も起こすため、脳卒中・心筋梗塞なども合併しやすくなります。 糖尿病の治療の目標は? 糖尿病治療の第一の目標は血糖値を良好にコントロールして合併症を予防することです。 コントロールの目安には血糖とグリコヘモグロビン(HbAic)の値を用います。 血糖値は採血した瞬間の値ですがグリコヘモグロビンは大体1ヶ月前の平均的な血糖の状態を反映しています。正常値は食前血糖 80~120 mg/dl、食後血糖 100~160 mg/dl、グリコヘモグロビン 5.5~6.0 %程度と考えられ、血糖値を正常に近づければ近づけるほど、合併症がでる心配が少なくなります。 特に、循環器疾患をお持ちの方についてはやや厳しい設定をする必要があり、通常は随時血糖で 170 mg/dl未満かつグリコヘモグロビンが 6.5 %未満というのがというのが一応の目標になります。 具体的な治療方法は? 糖尿病の治療の基本は、食事療法と 運動療法です。 肥満はインスリンの作用を妨害するので糖尿病にとっては大敵です。 栄養素をバランスよく取りながら標準体重を維持するため、食事療法が必要です。 また、弱まったインスリンの働きに合わせた食事の量にすることも必要です。 ブドウ糖をよく利用する筋肉を増やし、インスリンの作用を妨害する脂肪を減らす、また肥満を是正するなどの利点がある運動療法も糖尿病の治療には重要なものです。 中程度の全身運動(50歳代であれば脈拍が1分間に110程度になるような運動)を毎日3分以上おこなうと効果があります。 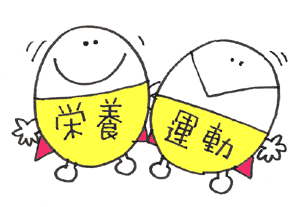 薬物治療 食事療法・運動療法で血糖値が十分に正常化しない場合、飲み薬やインスリンの注射が必要になります。 飲み薬には、強制的に血糖値を下げてしまう物や、食物の吸収を遅くする物などいろいろありますが、それぞれ内服方法が決まっています。間違った使い方は有効にならないだけでなく、逆に危険を伴うこともありますので、主治医の指示を守るよう心がけて下さい。 インシュリンの注射は不足するインシュリン量を予測して体外から補う物です。生活のリズムが安定していないとなかなか安定したコントロールが得られません。 糖尿病の検査 糖尿病であるかどうかの検査は「経口糖負荷試験」を行うのが一般的ですが、一定の検査結果が得られた場合にはそれだけで糖尿病と確定診断が付くこともあります。 糖負荷試験は、一定量のブドウ糖液を飲んだ後、2~3時間目までの血糖値の変化を調べる物で、下図のように糖尿病かどうかの判定をします。 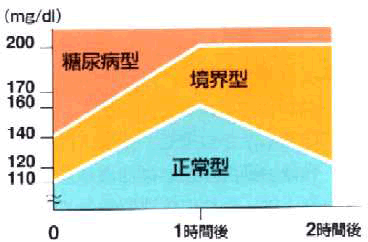 糖尿病のコントロール状態を知るため患者さん自身が、体重測定、尿糖測定、場合によっては血糖測定をする必要があります。この他、定期受診し血糖、検尿、グリコヘモグロビンなどの検査をします。 このうち、グリコヘモグロビンでは採血前の1ケ月間の平均的な血糖の状態がわかります。この他、いろいろな合併症に関する検査も定期的に受ける必要があります。 糖尿病と診断されても恐ろしい合併症がすぐ起こるわけではありません。 糖尿病を良好にコントロールすれば、健康な人と同じように長生きをすることができます。いいかえると、あなたは糖尿病を持ちながら、普通の人と同じように長い有意義な人生を送ることができるのです。 では、これから一緒にがんばりましょう! |
 糖尿病とは?
糖尿病とは?