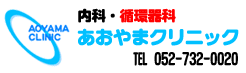
アルコールと肥満
適量とされるアルコール量のカロリー
 アルコールのカロリーは、身体の中で熱になるだけで、身体に蓄積しません。そのためエンプティ・カロリーとも呼ばれます。 お酒を飲んで肥満になるのは、お酒と一緒に食べた肴のカロリーが体内に蓄積するためです。アルコールは食事で取った脂肪の代謝を抑制することから中性脂肪が高い高脂血症の重要な原因とされています。そう言えば、酒の肴は見るからに高カロリーですよね。 また、適量とされるアルコールでも、肝臓がすべて代謝し終えるのに24時間近くかかるとされています。毎日晩酌される方は、肝臓が休み無くアルコールの分解を続けていることになります。理想的には48時間(=連続2日)全く飲まない日を作っていただくと、その後半24時間は肝臓を休めてあげることができます。  アルコールと虚血性心疾患 アルコールの飲酒量と全死亡率との関係を10年間にわたって調べた英国の研究がありますが、適度の飲酒者は全くお酒を飲まない人や大量に飲む人に比べ、長生きするとの結果でした。 適度のアルコールにより虚血性心疾患(心筋梗塞や狭心症)などの循環器系疾患の発病が減るのが主な要素とされています。適量のアルコール摂取には、善玉コレステロール(HDL-C)を上昇させる作用、血小板の凝集を抑制する作用や、ストレスから解放する作用などがあるためであろうと考えられています。 適当な飲酒量には個人差がありますが、一般的には日本酒では1日1合から2合、ビールなら大びん1~2本といわれています。 逆に1日3合以上飲む多量飲酒者は、虚血性心疾患による死亡率が逆に高いとの報告があります。「過ぎたるは及ばざるが如し」ですね。 また冠動脈が痙攣して胸痛を生じる冠攣縮性狭心症の方ではアルコールが引き金になる場合もあり、注意が必要です。 高血圧との関係 ふつうアルコールを飲むと、血圧が少し下がり、脈拍が増えます。 アルコールの代謝に関係している酵素の働きが遺伝的に弱く、飲むと顔が赤くなる人では、アルコールが代謝されてできるアセトアルデヒド(二日酔いの原因物質)が血液中に増え易く、その結果として血管が広がって血圧が低下し、さらに脈拍が増え易くなったりします。 また、長期的には大酒家は高血圧症になるリスクも高まることが示されています。肥満、塩辛いつまみからの塩分のとり過ぎなどの他に、血管の収縮性が亢進し、交感神経の緊張や、腎臓からマグネシウムやカルシウムが失われやすくなるためなどが原因と考えられています。 「百薬の長」とするために。 元来、日本人は全体としてはアルコールを分解する酵素が遺伝学的にはさほど多くない人種とされています。 一杯は人、酒を飲む。
二杯は酒、酒を飲む。
三杯は酒、人を飲む。
とのことわざのごとく、お銚子1本、ビール1本、グラス2杯のワインが薬の範囲と心得え、休肝日を作ってアルコールの長所をうまく利用しましょう。 適量のアルコールとは? 日本酒では1合/日
 ビールなら1本/日  ウィスキーならシングル2杯/日  ワインならワイングラス2杯/日  これらのうちのどれか1種と考えて下さい。 |
 アルコールとの付き合い方
アルコールとの付き合い方